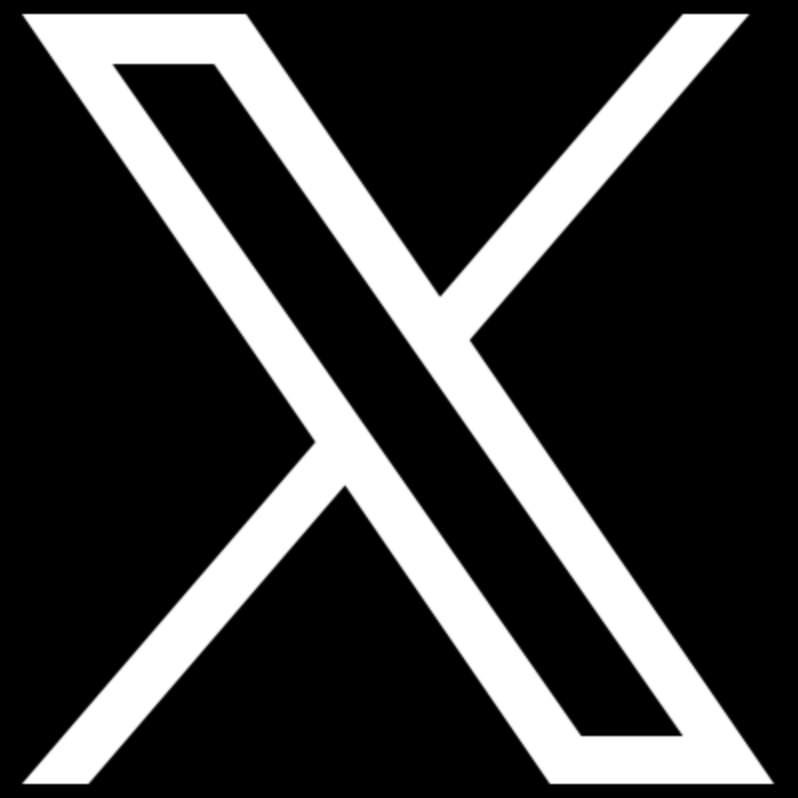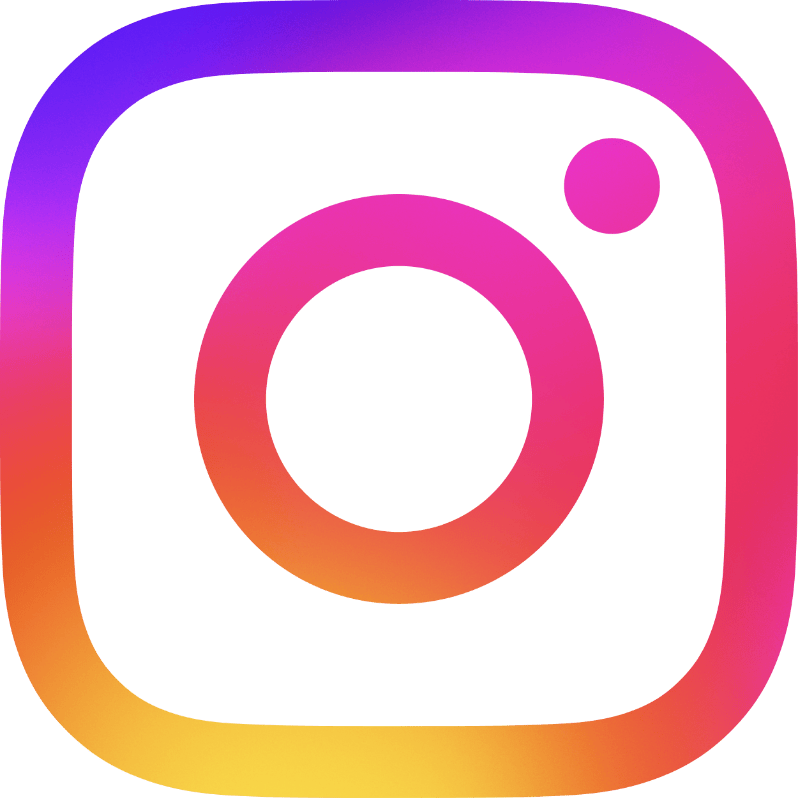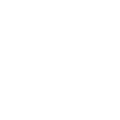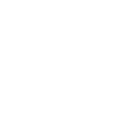フリーワード
診療科
用途から探す
受付時間
【午前】7:30~11:30
【午後】原則予約制
診療時間
【午前】9:00~13:00
【午後】14:00~17:00
面会時間
テレビ面会実施中
休診日
日曜日・祝日・12月30日~1月3日
診療実績クオリティインディケーター
診療実績
※診療報酬請求にかかる実績を示したものであり、各診療科で公表している内容とは異なる場合がございます。
クオリティインディケーター(QI)
クオリティインディケーター(QI)とは、医療の質を評価する目安となる指標のことです。 医療の質を数値で表現し、その数値を基に医療の過程や結果から問題点を見つけ出します。医療現場のデータを適切な指標で解析することで、診療の根拠となるものと、実際に行われている診療との格差の有無や程度を示し、医療の質改善のためのツールとして用いています。
| 共通指標 |
|
|---|---|
| 一般病棟 |
|
| 回復期病棟 |
|
QI向上への取組
当院では2016年度からQI指標を活用し、医療の質向上のための取り組みを行っています。
その活動報告として、当院の指標を一つずつ取り上げ、数値と活動内容を掲載した「QI News」を2ヵ月に一度発行していました。
2018年度からは年に一度、全ての指標の数値と活動内容を一冊にまとめた「新緑のQI」を発行しています。だれにでも分かり易いように難しい言葉は避け、図表や用語解説を入れています。また、活動内容については担当者からのコメントを掲載しています。ぜひご覧ください。
- 2023年度新緑のQI 2024.10更新
- 2022年度新緑のQI 2024.3更新
- 2021年度新緑のQI 2022.10更新
- 2020年度新緑のQI 2021.10更新
- 2019年度新緑のQI 2020.10更新
- 2018年度新緑のQI 2019.10更新
- QI News 第12号 臨床倫理カンファレンス・患者満足度について 2018.08.1更新
- QI News 第11号 新規入院患者における重症患者受入率・改善割合 2018.06.1更新
- QI News 第10号 手術患者に対する肺血栓塞栓症の予防対策実施率・術後発症率 2018.04.1更新
- QI News 第9号 入院患者のクリニカルパス適用率について 2018.02.1更新
- QI News 第8号 人工股関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率について 2017.12.1更新
- QI News 第7号 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率について 2017.10.1更新
- QI News 第6号 24時間以内の再手術率・予防的抗菌薬投与率について 2017.08.1更新
- QI News 第5号 退院後4週間以内の計画外・緊急再入院率について 2017.06.1更新
- QI News 第4号 救急車・ホットラインの応需率について 2017.04.1更新
- QI News 第3号 在宅復帰率について 2017.02.1更新
- QI News 第2号 入院患者の転倒・転落発生率と損傷発生率について 2016.12.1更新
- QI News 第1号 褥瘡推定発生率・改善率について 2016.10.1更新
TOP